
頭痛専門外来
頭痛専門外来とは
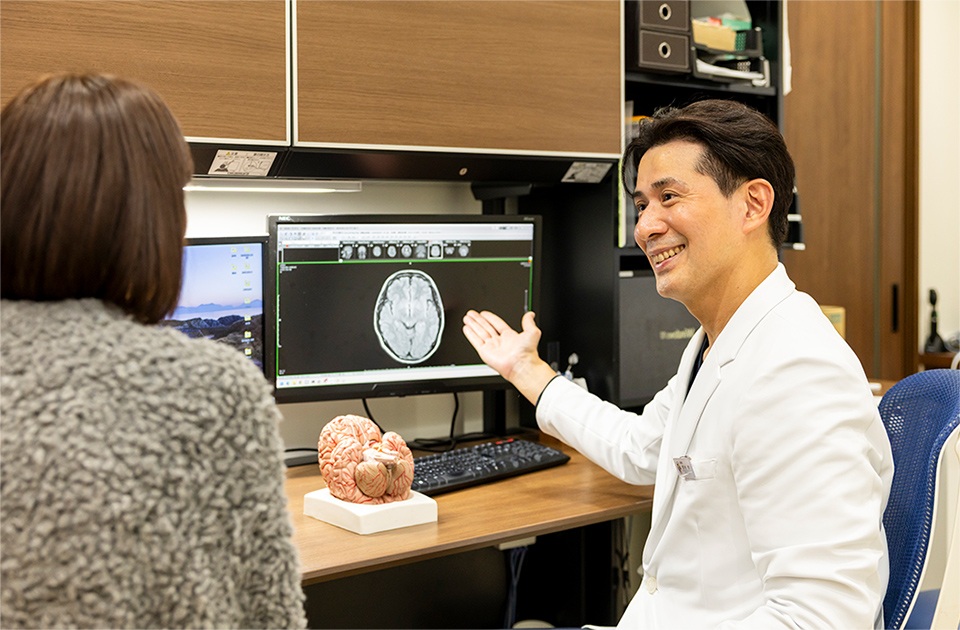
頭痛専門外来では、慢性的な頭痛や突然の激しい頭痛など、さまざまなタイプの頭痛に対して専門的な診断と治療を行います。 緊張型頭痛や片頭痛、群発頭痛だけでなく、くも膜下出血や脳腫瘍など命に関わる疾患が隠れている場合もあるため、早期の受診が大切です。
当院ではMRIなどの画像検査を活用し、原因を明確にした上で、一人ひとりに合った治療法をご提案します。頭痛でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
こんな方はご相談ください
以下のような症状に該当する方は、ぜひ当院の頭痛専門外来をご利用ください。
- 頭痛が続いており、不安や心配を抱えている
- 何度も頭痛薬を試したが、自分に合った治療法が見つからない
- 頭痛薬の使用頻度が多く、薬が効かなくなってきたと感じる
- 頭が重い、もやもやした感じが続いていて、集中力が低下している
- 突然、これまでに経験したことのない激しい頭痛が発生した
- お子様の頭痛が頻繁に起こり、心配している
頭痛の種類

頭痛は、その原因によって「一次性頭痛」と「二次性頭痛」に分類されます。
一次性頭痛は、明確な原因疾患がない頭痛です。多くの場合、片頭痛や緊張型頭痛、群発頭痛がこれに該当します。
二次性頭痛は、他の病気が原因で発生する頭痛です。脳出血やくも膜下出血、脳腫瘍など、命に関わる疾患が背景にあることもあります。
頭痛外来を受診される患者様のうち、約90%が一次性頭痛、10%が二次性頭痛です。以下に、それぞれの特徴を説明します。
一次性頭痛
片頭痛
脈を打つような「ズキンズキン」とした痛みが特徴で、しばしば吐き気や光・音・匂いに対する過敏症を伴います。
原因は三叉神経終末から分泌されるCGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)による脳血管の急激な拡張とされています。誘因には、ストレス、睡眠不足、気圧の変化、ホルモンバランスの乱れなどが挙げられます。
緊張型頭痛
精神的なストレスや眼精疲労、長時間のデスクワークが原因となることが多い頭痛です。
後頭部や側頭部に重い痛みや締め付け感を感じるのが特徴です。特にパソコンやスマートフォンの使用が多い現代では、患者数が増加しています。
群発頭痛
片目の奥や側頭部に激しい痛みが生じる発作性頭痛です。
15分~数時間程度の激しい痛みが1日数回起こり、1〜2ヶ月にわたって続くことがあります。夜間、睡眠中に頭痛発作がおこりやすく、頭痛発作時に眼の充血や流涙、鼻汁や鼻閉、瞼が下がるなどの症状が現れます。誘因として、飲酒、喫煙、急激な気圧の変化、不規則な睡眠などがあります。
薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛)
頭痛薬を頻繁に使用することで、脳が痛みを感じやすくなってしまい起こる頭痛です。
薬の効き目が薄れるだけでなく、逆に頭痛を誘発する悪循環に陥る場合があります。適切な治療と指導が必要です。
混合型頭痛
混合型頭痛とは、片頭痛と緊張型頭痛が同時または交互に現れる状態で、それぞれの特徴が入り混じっているのが特徴です。頭の片側がズキズキと痛む一方で、首や肩のこりを伴うこともあります。原因や症状が多様なため、両方に対応したバランスのよい治療が必要です。
二次性頭痛
くも膜下出血
くも膜下出血は、脳の血管が破れて、くも膜と脳の間に出血が起こる病気です。突然の激しい頭痛や意識障害を引き起こし、命に関わることもあります。主な原因は脳動脈瘤の破裂で、早期発見と迅速な治療が重要です。
脳出血
脳出血は、脳内の細い血管が破れて出血し、脳に損傷を与える病気です。高血圧が主な原因で、突然の頭痛、手足のまひ、意識障害などの症状が現れます。発症後の進行が早く、命に関わることもあるため、早急な治療が必要です。
脳腫瘍
脳腫瘍は、脳内やその周囲にできる腫瘍のことで、良性と悪性があります。頭痛、けいれん、手足のまひ、視覚や言語の障害など、腫瘍の位置や大きさによって症状が異なります。早期発見と診断が、治療や予後に大きく影響します。
頭痛専門外来の流れ
問診・神経学的診察
初診時には、患者様やご家族の病歴を詳細に伺います。
また、頭痛の発生頻度や強度、痛む部位、痛みの種類について詳しくお聞きし、必要な検査を提案します。
MRI検査
頭痛の原因を特定するために、必要に応じてMRI検査を実施します。
脳出血や腫瘍など、重大な疾患の発見に役立つだけでなく、副鼻腔炎や頸椎症といった間接的な原因も確認できます。
診断・治療
問診や検査結果に基づき、正確な診断を行います。
片頭痛の予防薬や神経伝達物質をブロックする注射(CGRP抗体薬)、緊張型頭痛の理学療法など、患者様に最適な治療を提案します。
生活習慣のアドバイス
頭痛の原因はストレスや生活習慣に起因する場合も多いため、食事、睡眠、運動、ストレス管理などについてアドバイスを行います。
継続的な診療
慢性的な頭痛には、定期的な診療で効果を見極めながら治療を進めます。
必要に応じてセカンドオピニオンをご希望の方にはご案内し、片頭痛予防注射のタイミング調整も行います。