
ふるえ
ふるえとは

ふるえとは、自分の意志とは関係なく手足や身体が震える状態を指します。多くの場合、ストレスや疲労、加齢によって一時的に起こることがありますが、頻繁に発生したり、症状が進行する場合には、神経や内分泌の異常、さらには特定の疾患が関与している可能性があります。
ふるえの影響は、軽度なものから日常生活に支障をきたすものまでさまざまです。症状が悪化すると、食事や文字を書くといった日常動作が難しくなることもあります。特に高齢者では、ふるえが進行性疾患の初期症状であることも少なくありません。早期に原因を特定し、適切な治療を受けることが重要です。
ふるえを引き起こす代表的な疾患
パーキンソン病
パーキンソン病とは
パーキンソン病は、中枢神経系に異常が起こる慢性の神経変性疾患です。特に、脳の「黒質」と呼ばれる部分で神経伝達物質ドパミンが減少することで、体の動きをスムーズに調整できなくなります。50歳以上の方に多く見られ、加齢との関連も指摘されており、日本でも高齢化の進行に伴い患者数は年々増加しています。進行はゆっくりで、早期に気づき治療を始めることで、症状のコントロールが可能です。
主な症状
パーキンソン病の症状は徐々に進行しますが、以下のような運動障害の4大症状がよく知られています。
安静時振戦:手や足がじっとしているときに震えるのが特徴です。緊張時や動作中には震えが軽減することがあります。
筋強剛(きんきょうごう):筋肉が固くなり、関節の動きがぎこちなくなります。動きが「ロボットのよう」と表現されることもあります。
動作緩慢(寡動):動きがゆっくりになり、歩き出すまでに時間がかかったり、小刻み歩行になることがあります。
姿勢反射障害:バランスを保つのが難しくなり、転倒しやすくなります。
このほか、表情が乏しくなる「仮面様顔貌」、声が小さくなる、字が小さくなるといった特徴も見られます。
また、便秘や抑うつ、睡眠障害、嗅覚低下など、非運動症状が現れることもあります。
治療方法
パーキンソン病の治療は主に薬物療法とリハビリテーションの組み合わせで行います。
薬物療法:ドパミンの働きを補う「レボドパ製剤」や、ドパミンの分解を防ぐ薬などが使われ、症状の緩和や生活の質の維持が期待できます。薬の効果には個人差があるため、症状に合わせて調整が必要です。
リハビリ・生活指導:歩行訓練や筋力維持を目的とした理学療法、バランス改善、言語訓練などを通じて、日常生活を安全かつ自立して送る支援を行います。
進行性の病気ではありますが、早期診断と継続的な治療によって、できるだけ長く自立した生活を送ることが可能です。
ご本人だけでなく、ご家族への支援も重要ですので、気になる症状があれば早めの相談が勧められます。
本態性振戦
本態性振戦とは
本態性振戦(ほんたいせいしんせん)は、原因が明確に特定されていない慢性のふるえの病気で、特に手や腕、首、声などに影響が現れます。最も特徴的なのは、コップを持つ、字を書く、食事をするなどの何かの動作をしようとしたときに震えが目立つ点です。これを動作時振戦と呼び、パーキンソン病のように安静時に震える「安静時振戦」とは異なる症状パターンです。遺伝性の要素があるとされ、家族内で複数人が発症するケースもあります。年齢とともに症状が強くなることがありますが、若年で発症することもあります。
主な症状
初期のうちは軽度なふるえで日常生活に大きな支障はありませんが、症状が進行すると、スプーンで食事をする、飲み物をこぼさずに飲む、書類に字を書くなどの細かい動作が困難になることがあります。震えは片手から始まり、次第に両手や首、声、あご、まぶたなどに広がることもあります。首の震えが目立つと、周囲からの視線が気になり外出を避けるようになるなど、心理的・社会的な影響が出る場合もあります。声の震えが強くなると会話がしづらくなり、コミュニケーションに支障をきたすこともあります。
治療方法
軽度の本態性振戦であれば、日常生活に大きな支障がなければ経過観察となることもあります。しかし、日常動作が困難になってきた場合には、薬物療法(β遮断薬や抗てんかん薬など)や作業療法・理学療法によるリハビリが検討されます。薬が十分に効かない場合や症状が重度な場合には、**脳深部刺激療法(DBS)**という外科的な治療が選択されることもあります。これは脳の特定部位に電極を埋め込み、電気刺激でふるえを抑える方法で、近年注目されています。
治療の目的は「完全になくすこと」ではなく、ふるえによる日常生活の支障を軽減し、QOL(生活の質)を維持・向上させることです。
バセドウ病
バセドウ病とは
バセドウ病は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで発症する自己免疫性の甲状腺疾患です。免疫の異常により、自分の甲状腺を刺激する抗体(TSH受容体抗体)が作られることで、甲状腺ホルモンの分泌が過剰になります。このホルモンは体の新陳代謝を調整する重要な役割を持っており、過剰になると全身の代謝が異常に高まるため、心身にさまざまな負担がかかります。特に20~40代の女性に多く発症し、ストレスや体質、遺伝的要因が関係するとされています。
主な症状
バセドウ病では代謝の異常により、手足の細かいふるえ(振戦)が現れることがあります。これに加え、動悸(心拍の速まり)や多汗、倦怠感、体重減少などの全身症状がみられ、特に暑がりになる傾向があります。甲状腺の腫れ(甲状腺腫大)が首元に触れるようになり、違和感を覚えることもあります。さらに進行すると、眼球突出(目が前方に突出する)や複視(二重に見える)といったバセドウ病眼症が現れることもあります。まれに、視力低下や眼の痛み・乾燥感などの症状が重くなることもあり、眼科的な診断も重要です。
治療方法
治療の基本は、薬物療法によって過剰な甲状腺ホルモンの分泌を抑えることです。抗甲状腺薬(チアマゾールやプロピルチオウラシルなど)が使用され、ホルモン値を正常範囲に保つことが目指されます。症状の安定には数ヶ月~1年以上かかることもあり、定期的な血液検査と医師の診察が欠かせません。薬の効果が不十分な場合や再発を繰り返す場合には、放射線治療(アイソトープ治療)や外科的な甲状腺切除術が検討されます。これらの選択肢は年齢や症状、妊娠希望の有無などを考慮して決定されます。また、ストレスの軽減や栄養バランスの取れた食事、規則正しい生活習慣も症状管理にとって重要です。治療を放置すると心房細動などの不整脈や心不全、骨粗鬆症のリスクが高まるため、早期診断・早期治療が非常に重要です。
ふるえの診断と検査
問診と初期診断
ふるえの現れるタイミングや状況、症状の進行具合を詳細に確認します。併発する症状(動悸、体重減少、筋肉の硬直など)の有無も重要な手がかりになります。
必要な検査
血液検査
甲状腺ホルモンの異常や糖尿病の有無を調べます。
神経学的検査
ふるえの種類やパターン(安静時・動作時など)を評価します。
画像検査
MRIで脳や神経系の異常を確認します。
ふるえでお困りの方へ
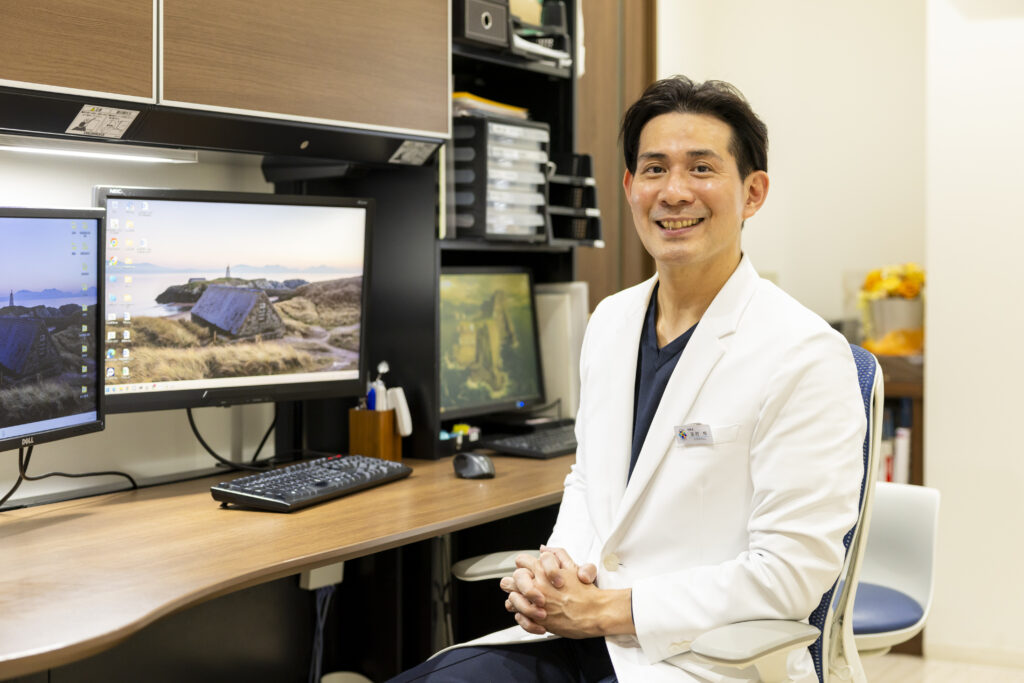
ふるえは、軽度であれば日常生活に大きな支障を与えないこともありますが、その背後に重大な疾患が隠れている場合もあります。特に、パーキンソン病やバセドウ病のように進行性の疾患では、早期診断と治療が症状の改善や進行の抑制に大きく寄与します。
「ただの疲れ」と見過ごさず、ふるえが続く場合や症状が悪化していると感じた場合は、ぜひご相談ください。